027:学生寮に暖炉があれば絶対無敵
Lumos!
以前のそれを覚えている方がいるかどうかは分からないが、ブログのタイトルを変えた。「theINGLENOOK」。炉辺・炉端など、総じて「火を囲む場所」を意味する英語である。具体的には、野外での焚火の周り、というより、暖炉の周り、という意味合いらしい。
火を囲んでいるうちに、不思議な感覚に陥ったことはないだろうか。身体の正面はあたたかく、背中はすごく冷たくなっていく。そしてパチパチと薪がはぜる音を前にして、饒舌になるか寡黙になるかは人によって分かれるだろうけど、いずれにしてもそこで紡がれる言葉や物語は、あるいは周囲の静寂でさえも、何だか物凄い熱量に充ちていくような、そんな感じ。「inglenook」という語からそんな情景を想起しながら、ほわっと「そんなブログにしたいなぁ」と今更ながら思ったりして、つまりは一目惚れしたのである。
一方、近頃「火」と言えば、ロンドンでの火事が大きく報じられている。冷蔵庫の爆発が火元とみられているが、2007年以前に建てられた高層住宅にはスプリンクラーの設置が義務付けられておらず、それも被害の拡大を後押ししたとBBCが報じている〈【ロンドン火災】 なぜ高層住宅にスプリンクラーがついていないのか - BBCニュース〉。
人類は、火を手に入れることで飛躍的に発展してきた。自然を社会化し、生存戦略を高度化した。つまり生身の身体ではできないような能力を、火や金属や文字は、人類に提供した。しかし、それはまさに有史以来の「取扱い注意」品目でもあり続けたのである。

マンチェスターで行われた歌手アリアナ・グランデのコンサートで、テロリズムの火の手が上がった。後日、市内で行われた追悼式典では、オアシスの代表曲「Don't Look Back In Anger」の合唱が自然発生する。下の引用は、その歌詞の一節だ。
So I'll start the revolution from my bedroom
Cos you said the brains I had went to my head
Step outside, summertime's in bloom
Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face
You ain't ever gonna burn my heart out
素敵な曲だ。もちろんこの歌詞に関しては、その背景にあるギャラガー兄弟の生い立ちなども含めて、色々な解釈、様々な解説があるけれど、僕はここではどれも支持しないことにしておく。ただあえてここまでの文脈に(ひどく乱暴に)引きつけるとするならば、「theINGLENOOK」というブログ名にこんな意味を込めてみたい。
While your revolutions start from every bed room
Sit around the fireplace, and listen to one another
学部時代、副学長がおっしゃってたことの中で最も印象に残っている言葉が、「孤独な時間が意外に大事」という旨のはなし。良い思索も良い学びも良いアイデアも、孤独なときに生まれやすいけど、その質はその孤独の質に左右されると。
忙しい日々から解放され、僕らは自分の「ベッドルーム」で、孤独に「革命」を起す。経済的に不自由であったとしても、精神の自由、想像力の自由まで明け渡してなるものかという気概で、例えば趣味に没頭したり、家族と時間を過ごしたり、日がな一日眠り続けてみたり、あるいは本を開いてみたりする。なら時には、その孤独の傍らで、誰かと火を囲んで話したりするのもありなんじゃないか。theINGLENOOK。
***
ところで、先ほど取り上げたアリアナ・グランデの誕生日は、1993年6月26日らしい(もうすぐだ)。実は、このブログを書くにあたって「6月26日」をwikipediaで調べていて偶然知ったのだが、何というか、まさか僕と同い年だったとは思っていなかったので少し驚いている(ちなみに僕は彼女の楽曲をただの一つも知らない)。
さて、今回問題にしたいのは、その彼女が誕生してちょうど4年後の、1997年6月26日のことである(ようやく本題に入れる)。言い換えるならば、今からちょうど20年前の、1997年6月26日。皆さん、何の日だか想像がつくだろうか。ちなみに少しずつ伏線を張ってきたのでお分かりのように、この日付に関係する場所は、「イギリス」である。
その日、その出来事は、ひっそりと起きていた。まるで僕のこのブログのように、誰の目に留まることもなく、それは過ぎ去ろうとしていた。本人としても、そうなることを予想していただろう。しかし、社会はそれを許さなかった。ただいずれにしても、1997年6月26日、その出来事はイギリスで静かに起きていた。その出来事とは、初版わずか500部での、J.K.Rowling『Harry Potter and the Philosopher's Stone』の刊行である。
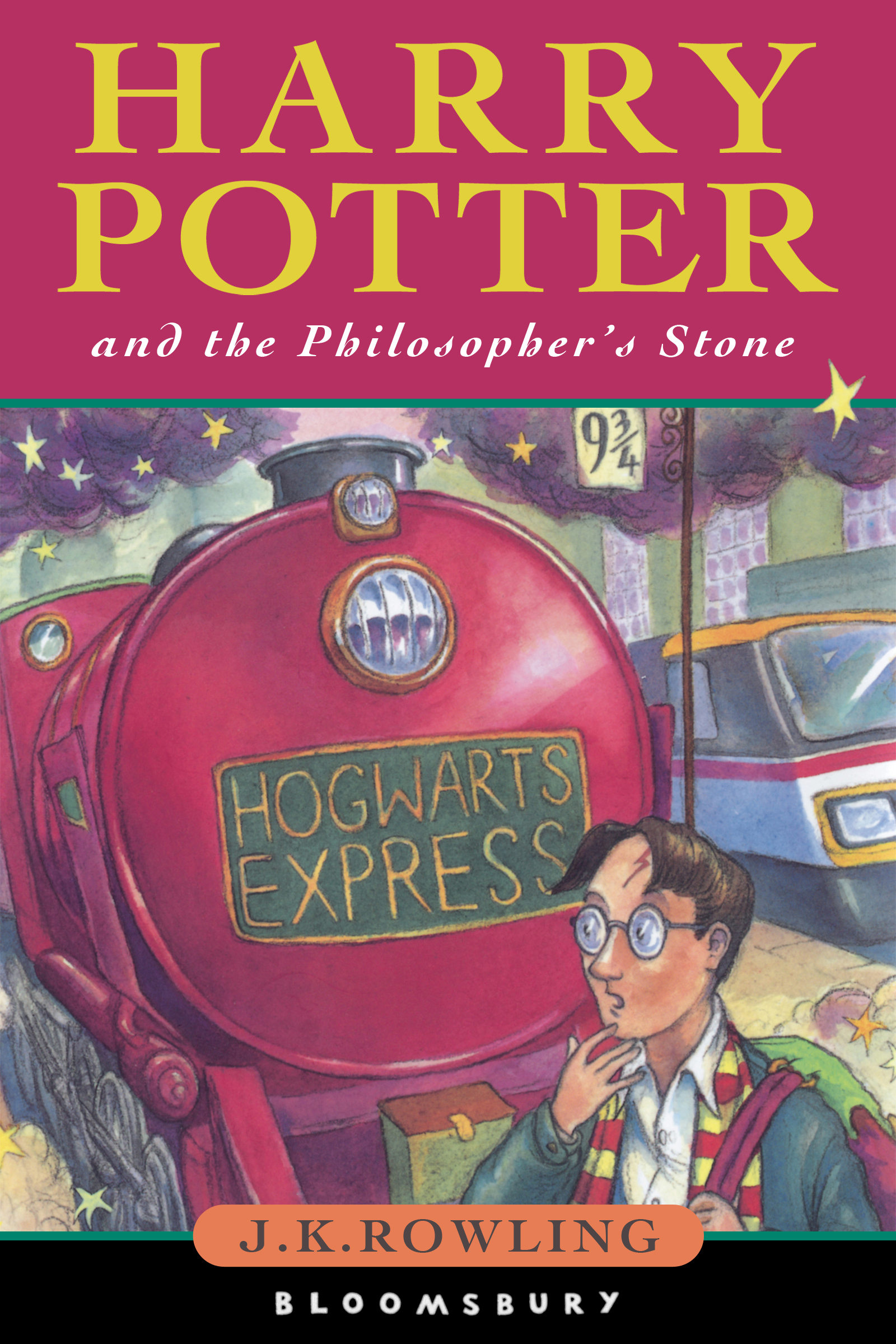
貧しいシングルマザーだったJ.K.ローリングの当時の苦悩が、作品の様々な箇所に影響を与えていることも有名だ。母親と死別し恋人との中が険悪になっていったときに思いついたのがクィディッチで選手に体当たりしてくる鉄球(=ボール名は「ブラッジャー」)だったことや、困窮と心労と鬱病で「自殺を考えた」という頃にはディメンター(=監獄アズカバンの看守)の着想を得ていることなど、私生活の苦悩なきところに創作の花は咲かないのだろうかと思わされる。
1作目『the Philosopher's Stone』の面白さは口コミでどんどんどんどん瞬く間に広がっていき、イギリス発売の3日後には、アメリカでの出版権をかけたオークションでなんと10万ドルで落札されている。その後のサクセス・ストーリーは誰もが知っていることだろう。2作目『the Chamber of Secrets』以降、発売日には世界中で長蛇の列ができた。ただ唯一、この1作目だけが、ひっそりとイギリスの書店に置かれ、読者との新鮮な出会いを果たしていたのである。
間もなく、それから20年が経とうとしている。
小中の僕を知る方ならご存知かとは思うが、当時の僕はハリー・ポッターの一読者を超えて、周囲の人に宣教師のごとく勧めていた。またハマっていたことは、「Yahoo!知恵袋」に投稿されるハリー・ポッターに関する質問にできるだけ正確に答えていくこと、そしてベストアンサーを獲得することだった。これが結構なベストアンサー率だったんだよなぁ(ほんと)。また、後にポーランド旅行の道連れとなる友人M(参照:015:ポーランドぐるぐるして、「リアルへの肉薄」を。 - FESTINA LENTE the 2nd)と共にクラス新聞『The Quibblers』を立ち上げては、好き勝手にやたらとハリー・ポッター特集を組むなど、クラス新聞の役割や意義などを一切無視していた。今でもその原稿は大切に取ってある。
今振り返れば、黒歴史と言えるかもしれない(笑)。しかしこれら「自分の考えを(人に読まれることを前提に)文章にする」という行動は、こうして細々とブログを書いていたり、ひいては文系大学院に進学しているように、現在の僕を形作る初期段階だったのだと思う。
だからこそ、僕にとっても、やはり「2017年の今」というタイミングを逃してはならない。そういう使命感のままに、今回は「ハリー・ポッター」について少し書いてみたいと思う。まずは、ハリー・ポッターと僕個人の関係について少し補足し、次に、映画『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』を昨年観てから考えていることについて。
1. Found My Own "Platform 9 and 3/4"
僕がこのシリーズに出会ったのは小学4年生の春。2003年のことだ。4月生まれの僕は、誕生日に『ハリー・ポッターと賢者の石』を買ってもらったのである。
実を言うと、それまで読書はろくにしたことがなかった。もっぱら図鑑や百科事典を眺めたり、それを見ながら絵を描いたりしていた僕に、「虫が好きだから」と母は『ファーブル昆虫記』や彼の伝記を買い与えてくれたりもしたが、やはり当時あまり活字を読むのが楽しくなかったのを覚えている。そんな僕がなぜあの分厚い本を、しかも誕生日プレゼントに選んだのか皆目見当がつかない。誰かクラスメイトが読んでいたのを真似したかっただけなのか、ただやはり全く思い出せないのだ。ただ一つ確かなことは、『ハリー・ポッター』を全く知らなかったという訳ではなかったということ。雨の日の学童保育で一度、映画版を観た記憶がある。だが、いずれにしても当時の僕にとっては、事実上「人生初のまともな読書体験」であったことに変わりはないのだ。
最初はすごくゆっくりと読み、100ページ進むごとに母に自慢しに行った。「いきなりこんな分厚いの読めるの?」とか何とか嫌味を言われて、意地になっていたんだと思う。そしてそんな風に思っているうちに何とか読み終え、それ以来、虜になってしまったのである。母親も後に読んで、「おもしろいね」と言っていた。

その後、どのようなハマり方をしていたのかについては、前述のとおりである。次に述べたいのは、『ハリー・ポッター』が具体的にどのように僕の日常生活に影響を与えていたか、英語学習に焦点を当てて、少し書いてみたい。
まず僕は英会話教室に6歳から通っていたが、浪人生活が終了するまで続けたので、13年3ヶ月間、毎週欠かさず通ったことになる。だからだろう、僕は調子に乗って原書『Harry Potter and the Philosopher's Stone』に手を出したりもした。
中2だったと思うが、新宿の紀伊国屋書店で母に買ってもらい、中学の教室でこれ見よがしに辞書を引きながら「読んで」いた。いや、実際は見ているだけだったに違いない。英会話を習っていたとは言え、文法もろくに体系的に学んでいない。読めたわけがない。だが、それで満足だったのだ(ただ、何度も何度も日本語版を読んでいたから、少なくとも一単語さえそのページで理解できるものがあれば、そこに書かれていることを推察することはできた。それが楽しかったのかもしれない)。
また英語の授業で新しい文法や単語を習ったとき、『ハリー・ポッター』の登場人物たちやその設定を引っ張り出して、習ったばかりの単語や文法を使った例文を作って遊んでいた。例えば「現在完了」の文法を習ったとする。すると、
- Harry:Professor, have you ever been to Godric's Hollow?(ハリー:先生、ゴドリックの谷に行かれたことはありますか?)
- Dumbledore:Of course, I have, Harry. In the first place, I lived there with my family when I was young.(ダンブルドア:もちろんあるとも、ハリー。そもそもわしは若い時にあそこに家族と住んでおったよ)
といった具合である。作中でハリーとダンブルドアが「ゴドリックの谷」について話し合う場面は(確か)無いのだが、ここでは自由に二次創作を楽しんでいた。これは3年弱続けたと思う。英語担当は2、3年次の担任でもあったが、提出するノートにそれを「連載」していたので、先生がそれに対してどんなコメントをくれるのかも毎回楽しみではあった。
そうやって僕は、義務として強いられている「勉強」を、自分の好きなもの/こととして、つまり自分独自のゲームに組み替えてこなしていたのである。ちなみにこのメソッドは、その英会話教室に併設されている学習塾で現在教えている中学生に、こっそり紹介したりしている。自分なりの「世界への入口」、いわば自分なりの「9と3/4番線」を是非とも見つけて欲しいと思う。
2. Why They Concealing Themselves?
J.K.ローリングは、2001年に『Fantastic Beasts and Where to Find Them』というスピンオフの本を出版している。同年『Quidditch Through the Ages』も刊行しており、日本でもそれぞれ『幻の動物とその生息地』『クィディッチ今昔』という邦題で静山社より刊行されている。前者の方は、昨年ローリング自身の脚本により映画化された。なんと5部作構想だそうなので、あと4作もある。
2008年7月に原作日本語版が『ハリー・ポッターと死の秘宝』で完結し(当時中3)、2011年8月に映画シリーズも『ハリーポッターと死の秘宝Part II』で完結し(当時高3)、「あ~これで終わりか」と思っていた僕にとって、
- 2014年7月、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の営業開始(当時大2)
- 2016年7月、『死の秘宝』の後日談を描いた演劇『Harry Potter and the Cursed Child(邦題:ハリー・ポッターと呪いの子)』の脚本発売(当時大4)
- 2016年11月、映画『Fantastic Beasts and Where to Find Them(邦題:ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅)』の公開(当時大4)
という一連の、一大資本主義的消費爆弾の投下は、正直言って嬉しい限りなのである。しかし、それにしても「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」っていう邦題の酷さには頭が下がる。一体どんなセンスしてんねん。そんでもって「ファンタビ」っていう省略の仕方。一体何がしたいねん。

この映画は、『ハリー・ポッター』の世界における新しい登場人物たちの物語である。原作は、魔法生物学者ニュート・スキャマンダーが世界中の魔法生物の生態について書き記した本という設定で書かれているが、映画ではニュートを主人公とし、経済的に大繁栄をしていた1926年の米ニューヨークを舞台に、物語は展開していく。
僕はこの映画が好きだし、とても楽しく観ることができた。ただこの年齢で、社会学を通じてある程度の社会に対する視角を手に入れていたからこそ、のことだと思う。過去の『ハリー・ポッター』シリーズは、自分が小中高時代を過ごしていたから、同じく学び舎での生活を送るハリーたちに、どこか自分を投影していたのだと思う。実社会から隔絶された閉鎖空間としてのホグワーツーーー。しかし『ファンタスティック・ビースト』シリーズでは、魔法使いと魔法界の問題が描かれる。そこにあったのは人間(英:マグル/米:ノー・マジ)の社会と同様の、社会階層と職業分化(①)であり、障害者差別と児童虐待(②)であり、人種差別主義者の扇動(③)であり、死刑のあり方の問題(④)であり、珍しい生き物の密輸(⑤)であったり。
ともかく、たくさんのテーマで溢れていて、それらはもはや社会問題であって、そういう意味では、善悪がハッキリと分かれていた『ハリー・ポッター』シリーズとは一線を画す描かれ方だったように思う。以下にそれぞれ言及してみよう。

▲アングラなバーで歌う小鬼(ゴブリン)の女(①)。一部の小鬼は英グリンゴッツ魔法銀行などで専門職に就くが、それ以外はいわゆる「水商売」をしている様子。

▲米国魔法議会(MACUSA)で杖磨きをする屋敷しもべ妖精の老人(①)。魔法族よりも社会的地位・賃金の低い仕事を担っている様子。

▲右が、魔法族の子でありながら魔法力を持たない障害者(スクイブ)のクリーデンス。孤児である彼は、引き取られた先の継母から身体的虐待を受けている(②)。左が、クリーデンスを虐待する継母メリー・ルウ。「新セーレム慈善協会」を組織し、ニューヨークでの治安の乱れの原因を「魔女の仕業」に帰結させ、社会的不安を扇動する非魔法族(③)。

▲「何故こそこそ隠れているのだ?」と問う。魔法界の存在を人間に知らしめ、戦争(?)を起そうと画策する欧州の闇の魔法使い・グリンデルバルド(③)。これはJ・デップで、次回以降若い頃の彼をM・ミケルセンが演じる予定となっている。ちなみにドイツ語風の名前のグリンデルバルドは、1945年にイギリスのダンブルドアに倒されることになっているのは偶然か、あるいはJ.K.ローリングの意図か。

▲死刑執行室。死刑囚は中央の椅子に座る直前に、「楽しかった記憶」を抜き取られ、座らされた後、この水面が見せるその「楽しい記憶」によって「幸せ」な幻視を見せられる。死刑執行という恐怖を奪いさり、自ら死を受け入れるように導かれる。つまりここでは社会から死刑囚を消すことが第一に重要視されており、死刑囚に苦痛を与えるという意味での「制裁」は目指されていない。功利主義的に見れば、死刑囚の苦痛が完全に回避されている上に、刑執行により社会の効用も上昇することになるので、これは「最善」の死刑執行方法ということになる。言い換えれば、死の呪文「アバダケダブラ」や魔法薬などでは大きな苦痛が伴うということだろう(④)。

▲Thunderbird(サンダーバード)。雷雨を呼ぶ巨大な鳥。米アリゾナ原産だが、密輸業者が運んでいる過程でエジプトに繋がれていたところを、主人公ニュート・スキャマンダーが救出した。彼はそもそもこの種をアメリカに帰そうとする目的で、そもそも大西洋を渡ってきた(⑤)。
という訳で、このパートのタイトル「Why Wizarding World Hinding Themselves?(邦訳:なぜ魔法界は自らの身を隠すのか?)」に立ち返ろうと思う。この問いは、前述したように闇の魔法使い・グリンデルバルドから提起されている。しかも重要な物語の最後に。
A law that has us scuttling like rats in the gutter, a law that demands that we conceal our true nature, a law that directs those under its dominion to cower in fear, lest we risk discovery. I ask you, Madam President, I ask all of you. Who does this law protect? Us? Or them? I refuse to bow down any longer.
その法のせいで我々は ドブネズミのように本当の自分を隠し コソコソと見つからぬよう おびえながら生きねばならない。議長にお聞きしたい。皆に聞こう。誰を守る法だ?我々[筆者注:魔法族]か?彼ら[筆者注:非魔法族]か?私はもう従えない。
どちらも字幕の写しだ。この問いかけに対して、米国魔法議会議長は沈黙する。むしろ答えに窮しているようにさえ見える。この演出に、原作者であり脚本として参加したJ.K.ローリングの、何かしらの意図があるのだろうか。
加えて、主人公ニュート・スキャマンダーからも、異なる文脈で同様の点の、つまり「何故そんなに隠れているんだ」的な指摘が見られる。以下は、米魔法界の政府における捜査官(=「闇祓い」)であるティナとの会話である。
Tina:Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America?
Newt:I do know a few things, actually. I know that you have rather backwards laws about relations with Non-Magic people, that you're not meant to befriend them and that you can't marry them, which seems mildly absurd to me.
ティナ:アメリカの魔法社会のことをご存知?
ニュート:人間との関係を定めた時代遅れの法律とか?友人になるのも、結婚も禁止なんて。
非常に興味深い。「魔法族は、なぜ、非魔法族から、隠れ続けているのかーーー」。
グリンデルバルドは人間社会と正面切って戦争をするために、魔法使いたちを解放するために「隠れるのをやめるべき」と主張し、ニュートは人間と交流しない理由がないし、それを規制する法律を時代遅れだと考えている。論理や主張は全く異なるが、どちらも棲み分けることに懐疑的という点では共通している。
J.K.ローリングは、確かに事細かく魔法界の歴史・制度・法律・習慣を設定しており、それは『ハリー・ポッター』シリーズにはもちろん、その他スピンオフ作品の端々にもそれらが登場する。世界観が統一されていることが、この作品のように、本編終了後のスピンオフ作品制作とその成功にも寄与しているのかもしれない。
ただし、ここでグリンデルバルドやニュート・スキャマンダーが提起するように、例えばこの問題、つまり魔法界における「共生の哲学」については、説得力のある説明は正直言って無い。この点については考えてみる価値はありそうだ。
まず、従来の『ハリー・ポッター』シリーズにおける英国の魔法界における基本的な事柄・前提を確認しておく。
- 魔法界では、基本的に「非魔法界に気づかれないこと」が前提に回っている。それは中世における魔女狩り等、魔法族にとっての迫害の歴史/経験に由来する。したがって意図的に気づかれること、例えば非魔法族の人間の前で魔法を使うことは非合法である(例:第5作、ハリーが従兄ダドリーの前で守護霊の呪文を使った際、彼がホグワーツ在校生だったからでもあるが、一度ホグワーツ退学を通知されている)。
- しかし魔法族には非魔法族の人間と婚姻関係を結ぶ者もおり、また非魔法族の人間同士から魔法族が誕生する場合もある(例:ハリーの母親リリーや親友ハーマイオニーは、マグルの両親から生まれている)。したがって個人的関係において、魔法族が自らの正体や魔法界の存在を明かすことは、ある程度許容されていると考えられる。また英国魔法界の政治的トップである魔法省大臣が交代した際や、魔法界での問題が非魔法界に影響を与えることが想定される場合は、魔法大臣本人が英国首相本人の執務室に一報を入れることが慣例になっている(例:第6作第1章、英国首相側の目線で魔法界との邂逅が語られる)。したがって建て前では白黒がはっきりしているが、実質的にはグレーゾーンも多い。
- 魔法族の中には、魔法族同士から生れた者を「純血/pure blood」と礼賛し、魔法族と非魔法族の人間の間から生まれた者を「混血/half blood」と呼称し、非魔法族の人間から突然変異的に生まれた者を「穢れた血/mudblood」と侮蔑するような、優生思想主義者・血統主義者がいる(例:由緒ある家系の中でも、闇の魔術に通ずる魔法使い・魔女に多い傾向。ヴォルデモート卿、マルフォイ家、レストレンジ家、ブラック家などが典型。しかしヴォルデモート自身は「純血」の父とマグルの母の間に生まれた「混血」であるなど、生い立ちへのコンプレックスを匂わすような設定も見られる)。ちなみに「穢れた血」に相当する魔法族の、ポリティカル・コレクトな呼称は「マグル生まれ」である。
- 魔法族には、非魔法族の人間(英:マグル/米:ノー・マジ)や彼らとの何らかの関係を持つこと/者に対して、前述のように(A)差別的な態度で接する者(=彼らを毛嫌いしていることを自らで自覚している者)、(B)好意的な態度で接する者(=彼らに関心があると自らで自覚している者)、そして(C)特に無関心である者。この3つの類型がある。
- 好意的な態度で接する者(B)は、人間の言語を理解し操ることのできる「知的魔法生物」(例:ケンタウルス、巨人、小鬼、屋敷しもべ妖精など)に対しても、好意的・寛容に接する傾向にある。ただ(B)の中でも、歴史的に構築された差別意識を無意識に有している者もいる(例:第4作、マグル生まれというある種のマイノリティであるハーマイオニーは、ホグワーツで働く屋敷しもべ妖精の権利向上に努め、運動の展開を試みた。ハリーもそれに対して一定の理解を示したが、(B)の家系であるがいわば「純血」の魔法族の生まれであるロンは、ハーマイオニーの運動に対して、「常識」の点から笑い飛ばしている)。
大体こんな感じだろう。言い換えれば、(A)は保守派の中でも比較的ナショナリスト的態度を取る者、(B)は他者への寛容を説くリベラリズムを重視する者、しかし(A)と(B)は明確に二分できず、いわばグラデーションのように分布すると考えられる。さてさて、そこで問題にしたいのが、(B)に哲学はあるのか?という点である。
翻って、僕つまり非魔法族の世界、特に欧米社会において、その哲学に相当するのがリベラリズムである。リベラリズムは有色人種・女性や性的少数者(LGBT)・障害者など、それまで「他者」「社会的弱者」として、社会的排除を構造的に強いられてきた人々を、一体どのように包摂し、共生していくか、その原理や方法をずーっと考え続けてきた。そしてこれは基本的に、政治的左派の中核的思想であり続けてきた。僕が思うにその重要な点は、以下の2点を暴くことが基本姿勢である。
- 排除されている特定の属性の人々(=前述のような少数者)は、マジョリティに対して「その属性を理由に劣っているようなことはない」という点
- したがって、一部の伝統・常識などによるその属性に所属する人々の排除は、「差別であり、不当である」という点
つまりこの2点が、差別を告発する上での手順となる。すなわち、「私たちは同じ人間である」と明らかにできるから、「みんなは自由だ平等だ」と宣言することができるのである。

では、魔法界と非魔法界の関係はどうだろう。
まず大前提が覆るだろう。魔法使いや魔女は、非魔法族(=人間)とは明らかに異なる。魔法界に社会学者がいたとして彼らがどんなに頑張ろうと、物語を追う限りでは、魔法使いと人間の間では、その性質(感情や知能)は同じだとしても、その能力(=できること)には大きく差異がある。言うなれば、杖さえあれば魔法使いや魔女は、死者を生き返らせること以外のほとんどの全てをすることができる。
だとすれば、中世の時代から何故彼らは、人間から隠れ続けてきたのだろうか。極端なことを言えば、クロマニヨン人がホモ・サピエンスとの競争に負けて滅び去ったように、ホモ・サピエンスを魔法族が根絶やしにしてもおかしくはなかったはずだ。しかしそうはしなかった。「できる」からと言って、それが彼らの「正義」にはならなかった。むしろ「できる」からこそ、その能力を隠し、あえて非魔法族との共生を図ることが規範となり、そしてそれに基づく法も制定され、機能しているように映る。
僕らの世界では、往々にして「出来るか否か」で、強者と弱者を生み出してきた。勉強できる人間は、良い学歴・良いキャリアを積むことができるシステムが作られている。だからこそ、その格差を是正するために再分配の仕組みとしての社会保障制度はある。一方で「労働力が無いから」と、身体・精神・知的障害者は「邪魔者」として扱われてきたように、性的少数者は「子孫を生まないから」と、また有色人種たちは「野蛮で、啓蒙されていないから」と、堂々と差別して良いことになっていた。
そうであるならば「魔法が使えないから」と、魔法使い・魔女たちが非魔法族を虐げたとしても何らおかしくはない。明らかな事実として、つまり常識や伝統による神話としての「差異」ではなく、相対化不可能で絶対的な能力差が、そこにはある。生物種としての、大きな違いがある。もはや、そこで起きるのは「差別」ではないはずだ。ゴリラを人類が檻の中に閉じ込めておいても「良い」とされるように、人類を魔法族が鎖につないで奴隷労働をさせても「良い」とされていたかもしれない。
読者や映画の観覧者は、「魔法族が『非魔法族との共生』を規範として共有している」ことを前提しすぎているのだ。この問いが、ここにきて、つまり『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』を観て始めて、僕の中に浮上した。
「魔法界における〈共生〉の哲学」とは、一体何か。
今は、本を全て読み直す時間もないわけなので、きちんと検討することもできない。したがって、是非とも映画の続編では、その辺りの考察が進むようなストーリーテリング、あるいはテーマ設定をしてもらいたいなと思っている。

手がかりになるのは、「一番最初の魔法族も非魔法族から生れたであろう」と想定すると、だからこそ魔法族は異分子として差別・迫害を繰り返されてきたであろう、という想定からは逃れられないということだ。したがって考えを覆して、ちょっと独自に推測をしてみることにしる。
例えば、魔法族から非魔法族が生まれたのかもしれないと想定してみる。そしてかつての魔法族が、過去に非魔法族(いわゆるスクイブ)を差別しては迫害を繰り返し、社会から排除していったとすれば、スクイブの2世3世たちが、ひいては10世たちが魔法族のことを忘れ去り、人間のみで成立する社会を形成していったとしてもおかしくはない。そして次に人間の側が、魔法族という異分子を「再発見」し、大規模な魔女狩りをしたとしたらどうだろう。そしてその時には、むしろ魔法使いの側が、人間社会の側に大きく依存しなければならなくなっていたとしたら。
その証拠に、魔法使いたちは非魔法族と基本的に同じものを食べ、同じ言葉を使う。例外は魔法界のお菓子程度に限られていて、そのほとんどが重複している。2つの集合の大部分が重なっているベン図のような、そんなイメージである。もし大昔にスクイブが魔法族と袂を分かったのならば、食事や言葉遣いまでも、それぞれに独自の文化圏が形成されていたに違いない。
だとするのならば、もしかしたら魔法族は、〈非魔法族との共生〉という名目で、非魔法族を構造的に支配し、その関係を一方的に維持することによって、非魔法族に生活必需品(食糧・衣服・インフラその他)を生産させているとは考えられないだろうか。そのような意味で、魔法族は、というか魔法省は〈非魔法族との共生〉を規範として内面化し、あまつさえ制度として完成させてきたのではないか。
嗚呼、まるでどこかのディストピア系SF小説みたいだ。そしてファンタジー小説的な「夢」が全くない。でもこれはこれで面白い、とも思う。クマノミとイソギンチャクのような相利共生ではなく、「魔法族による非魔法族への片利共生的関係性」ーーー。ただこれでは切りがないので、取りあえず今回は、ここで思索を一旦止めることにする。
Nox!